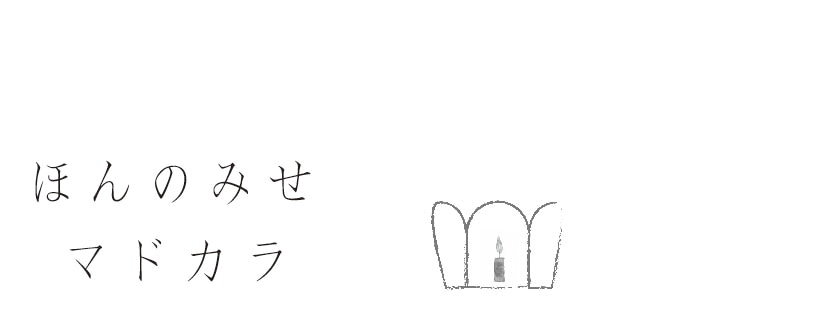-

【古本にて入荷】ドームがたり
¥1,760
アーサー・ビナード 作 スズキコージ 画/玉川大学出版部 2017年3月発行 *委託先で展示していた本です。カバーに多少のヨレがあります。 「あいにきてくれて、ありがとう」かつては広島の物産品を展示し、多くの人で賑わいつつも、戦争、原爆投下を経て原爆ドームと呼ばれるようになりながら、100年以上も広島を、核兵器使用後の世界を見てきた「ドーム」が語るものがたりです。 ドームはあの日、たくさんのつぶつぶが降ってきたのを見ました。たくさんのつぶつぶはウランのカケラで、小さすぎてからだに刺さっても痛さを感じない。あの日から骨組みだけになって、いろいろなものが見えるようになったドームには、遠くの街にもカケラやカケラをたくさんつくる「原爆」「原発」が増えていくのが見えています。 だいじょうぶかな、僕のまわりにいてくれるあの子や、ネコやイヌや、アオサギや、ミミズや、世界中のいきものや草や木にカケラがささらないかな… ドームは今日も誰かが来てくれるのを喜んで、静かに語りかけてくれます。そして心配もし続けています。悲しみをただちに終わらせるように、あのカケラを増やさないように。

-

【古本再入荷】写訳 春と修羅
¥1,500
SOLD OUT
宮沢賢治 齋藤陽道/ナナロク社 2015年2月発行 160ページ サイズ178 x 130mm 宮沢賢治「序」「春と修羅」「告別」「眼にて云ふ」の四篇の詩を、齋藤陽道さんの写真によって「画」に翻案された本です。齋藤さんのエッセイ「夜と歩いたこと」も収録。 「写訳」とは齋藤さんによる造語です。主に東北で撮られた写真を中心に、宮沢賢治の詩を齋藤さんの写真で翻案(既存の著作物を、形式を変更して新たな著作物を制作する手法)した1冊です。言葉と写真、向こう側からこちらを見つめる眼…ふたりが綴る新しい「春と修羅」です。 巻末には若松英輔による解説「言葉を写す詩人たち」が収録です。

-

よるのえ
¥1,100
SOLD OUT
キューライス/大和書房 2022年3月発行 イラストレーター・漫画家のキューライスさんによる、散文の添えられたイラスト集です。 すべてのものがいきいきとかわいいイラスト(漫画などでおなじみのキャラクターも登場)と同じページにある文は、気もちの泉に黒のインクが一滴落ちてしまったような、なんともシュールな世界観。しかも「あれ、なんでこの絵が…」というものも、不条理もたくさん。 でも遠い世界の話ではなくて、記憶のどこかにありそうな、なさそうな…ほら、目の前の石は知ってる誰かにどことなく似てたりして… 夜がだんだん長くなり存在感が増してきた季節。一日のいろいろを終えたあとで、となりの世界をのぞいてみませんか。

-

橋の上で
¥1,000
湯本香樹実 文・酒井駒子 絵/河出書房新社 2022年9月発行 いっそのこと、ここから逃げてしまったら・・・ ぼくが川を見つめていた橋の上で、ぼくに声をかけてきた知らないおじさん。 ぼくが心に抱えていたものを、またかつておじさんも抱えていたのだろうか。 おじさんが教えてくれた、水の音、みずうみの風景。 生きづらい世の中で、あの日があったから、 あの出会いがあったから、今の自分がある。 橋、だれかとだれかの間をつなぐ道の物語です。

-

ケの美 あたりまえの日常に、宿るもの
¥1,500
SOLD OUT
佐藤卓 編著/新潮社 2018年10月発行 「ハレ」と「ケ」とはよく耳にする言葉。「ハレ」」の日はお祝いをしたりお祭りがあったり、ごちそうをいただいたり、と特別な時間。しかしそれは、特別ではないいつもの時間があってこそで、その特別でない時間は無為でつまらない時間かというと、決してそうではないのです。「ハレ」と「ケ」は表裏一体、ケ=日常があってこそのハレではないかと思います。 この本は、ハレとケの中からあえて「ケ」の中にある、日々の自分の生活にとって愛しいもの、美しいと思うものを集めた展覧会「ケの美」展に出展された14人の方々の展示を書籍化し、あわせて展覧会企画者の佐藤卓さんと、美術についての解説やライターである橋本麻里さんの対談を収録されています。 わたしの日常の中でいつもともにあるもの、愛すべきもの。そんないろいろを思い浮かべながら読んでください。

-

四季の行事食(全集 伝え継ぐ日本の家庭料理)
¥2,600
(一社)日本調理科学会 企画・編集/ (一社)農山漁村文化協会 2021年12月発行 四季のある日本には、季節の行事に合わせて伝えられた食や食文化があります。節句、お花見、田植え、祭り、お盆、報恩講・・・それらは地域の住民がともに作り、祝い、祈り、伝えてきた文化です。 この本では、その中でも昭和35年から45年の頃に実際に地域に定着していた食文化のうち、「次世代にも作り食べ続けていってほしい」と願われて選ばれた食を収録したシリーズ「伝え継ぐ 日本の家庭料理」のひとつです。南北に長い日本に伝わってきた、その土地ならではの食材が使われたさまざまな行事食のほか、ひとの成長、お祝い、別れ、先祖への想いを表す「冠婚葬祭」の時に地域に伝わってきた食文化も収録されています。 たとえば、広島の多くの地区では4月3日は「お花見」の日として、お弁当やカラフルなニッキ水を持って山に出かけていたそう。野菜が年中食べられるようになり、年間を通して一定の温度で快適に過ごすことで四季の概念が薄まりつつある今日、食だけでなく、なくなりつつある地域の文化や行事なども、次世代に伝えていければ、と思えます。 もちろんレシピも満載。素材を「使い切る」料理がたくさんです。

-

ひと皿の小説案内 主人公たちが食べた50の食事
¥1,300
ダイナ・フリード 著・阿部公彦 監修・翻訳/マール社 2015年2月初版・2015年10月第2版 小説や絵本の中に出てくる「食べ物」、挿し絵を頼りに、想像や時には妄想を広げて、頭の中にいつまでも印象深く残っていたりしませんか? 著者のダイナ・フリードさんもまたその一人。デザインの企画で、小説に出てきた食を実際に調理して再現し撮影する中で、その楽しさに夢中になり、企画終了後も取り組み続けたそう。白鯨、ガリバー旅行記、百年の孤独、不思議の国のアリス、変身、風と共に去りぬ・・・この本には50の小説の食シーンが再現されています。 食も読書も、どちらも心地よく心身に摂取し、気もちのよいものという共通点がある、とは著者のことば。なるほど!そのワクワクが、どのページからもあふれてくる楽しい本です。 食の写真とともに、そのシーンが小説から引用されていたり、作品の豆知識や、巻末にはあらすじも収録されているので、一風変わったブックガイドとしても活用できます。 赤毛のアンの「いちご水」、その味やきっときれいな色、何度も頭の中で妄想しました・・・

-

森の絵本
¥1,000
SOLD OUT
長田弘 作・荒井良二 絵/講談社 1999年8月発行 どこかから聞こえる声。小さいけれど澄んだ、気もちのいい声。 きみの大事なもの、きみの大切なもの、忘れてはいけないものを探しに、深い深い森の中へ行こう- 大事なもの、大切なものは目に見えにくいけれどたしかにあって。わたしのそれはきっと派手ではないし、大きい声で話しかけてもこなくて、よく見失いかけてしまうのだけど。 それは森の中にある、と。じゃ、その森はどこにある…? 長田弘さん、荒井良二さんのタッグの、やわらかくて静かで優しいのに力強い絵本です。
-

アンネの木
¥800
SOLD OUT
イレーヌ・コーエン=ジャンカ 作/マウリツィオ・A.C・クゥアレーロ 絵 石津ちひろ 訳/くもん出版 2010年12月発行 オランダ・アムステルダム。1943年から1945年、ユダヤ人のアンネ一家が迫害から逃れながら生活していた「隠れ家」の前に生えていたマロニエの木が語る戦争の証言です。 遠くから戦争が近づくにつれ、「してはならない」ことが増えていき、やがて「存在してはならない」とされたユダヤの人々。息を潜めながら生きるアンネは、窓から見えるマロニエの木を生きる同志として希望を重ねていましたが… 今でも読み継がれる「アンネの日記」、アンネ・フランクの中にもたびたび記されたマロニエから見た戦争です。 このマロニエの木は実在していましたが、2010年の台風で倒れて一生を終えました。しかしこの苗木は世界中に渡り、日本では福山市などで今でも戦争の無意味さ、平和の尊さを伝えています。
-

あまの川 宮沢賢治童謡集
¥1,100
SOLD OUT
天沢退二郎 編・おーなり由子 絵/筑摩書房 2001年7月発行 「宮沢賢治さんの童話には、たくさんの、魅力的なウタがちりばめられています。かねてからわたしは、それらのウタはみんな、独立して読み味わわれるのを、待っているような気がしていました。」(【はじめに】より) 宮沢賢治が生前に唯一発表した童謡「あまの川」をはじめ、数々の童話の中に登場したうたを、自らも詩人で宮沢賢治の研究者でもあった天沢退二郎さんが編み、作家で絵本も多数手がけられるおーなり由子さんが、やわらかな絵を添えられています。そのうたからは、木々や動物、星たちのなかにいきる自分もまた自然のなかの小さなひとりだと思えるよう。 「風の又三郎」「双子の星」などの童話から48のうたが集められた1冊。声に出して読んでもリズムが心地よく楽しい本です。

-

にっぽんのおやつ
¥880
白央篤司/理論社 2016年3月 第2刷 「3時のおやつ」はだれもが楽しみにする食文化のひとつです。しかし端から端まで、全長3000キロを超える日本列島。気候も文化もそれぞれ違って当たり前。ならば、47都道府県の「おやつ」にはどんなものがあり、何を楽しく食べたのか。フードライターの白央篤司さんが取材されて、「写真絵本」としてつくられた、どのページにも幸せがつまった、ワクワクする1冊です。 お菓子や甘いものといった、一般的に考えられる「おやつ」以外にも、その地方以外の人には知られていない名産や、おすそわけしたりされたりする特産物、おみやげとしていただいたことのあるお菓子など、さながら47都道府県それぞれが自慢したい「わたしの暮らす場所のおいしいもの」の図鑑のようでもあります。目次はありませんが、最終ページの日本地図に書き込まれた「おやつ」一覧が、社会の授業のように、食べたことのある地方を別の色で塗ってみたくもなったりします。まだ食べたことのないおやつ、いくつくらいあるでしょうか? ※見返し部分にゆるめの折り跡がありますが、全体的に大変美品です。ご了承ください。
-

スペクテイター Vol.43 「わび・さび」
¥1,000
SOLD OUT
エデエィトリアル・デパートメント 2019年2月発行 「わび」「さび」本来は別の言葉であるこの二つの言葉。「閑寂」なイメージが浮かびつつも、説明するとなるとなかなか難しいものです。 ひとつのテーマについて、その導入部分から深く掘り下げ、さらに自分のものにするための提案までを1冊で扱う雑誌「スペクテイター」、43号のテーマは「わび・さび」。ずばり「わび・さびとは何か?」から、わび・さび探し、歴史、インタビュー、書籍案内などを多数のイラストや写真を交えて語る特集号です。 早回しで15秒の中にあらゆるものを詰め込むせわしない世の中、一輪の花や今宵限りの記憶の中だけにとどめるのもまた「わび・さび」、表紙の白椿のはかなさと凛とした佇まいは、息をのむような美しさです。

-

トキワ荘マンガミュージアム-物語のはじまり
¥1,540
SOLD OUT
コロナ・ブックス編集部 編/平凡社 2021年4月発行 「トキワ荘」とは、手塚治虫はじめ藤子不二雄、赤塚不二夫など現代漫画の基を作った有名漫画家たちが、青春時代を互いに切磋琢磨しながら暮らしたアパート。2020年、そのトキワ荘が外部・内部とも忠実に再現された「豊島区立トキワ荘マンガミュージアム」が開館しました。 この本は、そこに暮らし巣立ち、漫画界を背負っていった著名な漫画家たちの貴重なインタビューはじめ、暮らしぶりを自ら描いた漫画、当時のご近所である地域の人びとから見たトキワ荘、そしてミニコラムなど、さまざま角度からトキワ荘を見つめ紹介するマンガミュージアムのガイド本です。当時の写真も、ミュージアム内の写真も満載の、ファンには見逃せない内容です。

-

空の絵本
¥1,100
SOLD OUT
長田弘 作・荒井良二 絵/講談社 2011年10月発行 雨が落ち始めた。だんだん雨は強くなる。空の色も、あんなに青かったのに暗くなる。やがてだんだん雨は弱くなり、空の色がまた変わってきた。そのうち美しい夕焼けを追うように暗闇がやってきた。鳥たちが帰ってきて、こかげの色も変わってくる。1日が終わる、すべては運命のように。 長田弘さんのリズムある言葉に、荒井良二さんの深い深い絵。目で追っても、声に乗せて読んでも。やがてくる夜の静けさを思い浮かべる、味わい深い絵本です。

-
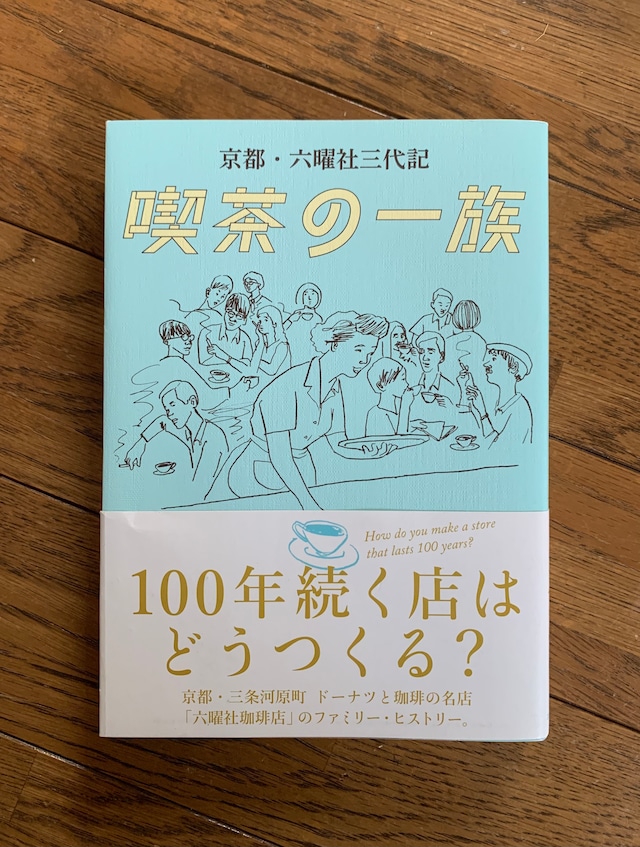
【再入荷】京都・六曜社三代記 喫茶の一族
¥1,100
SOLD OUT
樺山聡 取材・文/京阪神エルマガジン社 2020年9月発行 コーヒー好きが日本一多いともいわれる京都。ここで70年以上にわたってコーヒーを提供し続ける喫茶店「六曜社」の創業から今日、そして未来へもわたる家族の物語です。 物語のはじまりは、創業の1950年より数年前、終戦直後の1946年、満州。この地で出会った創業者の奥野實さんと八重子さんが、帰国を果たして京都に開く喫茶店「コニーアイランド」「六曜社」。高度経済成長、バブル期、平成の時代からやがて来る創業100年までを、主に創業社の妻、八重子さん、息子の修さん、孫にあたる薫平さんを軸に、奥野家の一族と周りの方々とともに描きます。 今日味わう1杯のコーヒー、そこにはたくさんの方の手から手をわたる仕事と思いがあります。家族が健やかに暮らすために、足を運んでくださるお客さまが楽しまれるコーヒーに、仕事に情熱を注ぐ奥野一族のお話は、だれの身近にあるお話でもあります。

-

鹿踊りのはじまり(日本の童話名作選)
¥1,000
SOLD OUT
宮沢賢治 作・たかしたかこ 絵/偕成社 1994年2月発行 宮沢賢治の故郷、岩手県花巻市に伝わる民俗芸能「鹿踊り(ししおどり)」は、地域の平安と悪霊退散を願う舞で、岩手県の無形民俗文化財に指定されています。 その鹿踊りのなりたちを、「わたくしはこのはなしをすきとおった秋の風から聞いた」と語られる、とてもユーモラスながら、美しい自然への畏敬の念・関わりについて考える物語です。 膝を痛め湯治に出かける嘉十は、食べきれなかった団子を鹿に与えた野原に忘れた手ぬぐいを取りに戻ります。美しく波打つようなすすきの野原で、6匹の鹿は、おそるおそる手ぬぐいに近づき「おまえはだれだ」と言わんばかりに・・・その様子をすすきの野原にひそんで見ていた嘉十は、手ぬぐいを囲む鹿のうつくしい歌と踊りに、つい心が躍って・・・ たかしたかこさんの描く、短くなる秋の午後のはかなさや繊細さ、白く光るすすきの野原にいきいきと舞う鹿、嘉十の心情。長い時間遺されている自然や民俗文化を考える物語絵本です。

-

美しく青き道頓堀川(桂三枝の落語絵本シリーズ1)
¥880
桂三枝 著・黒田征太郎 絵/アートン 2005年8月発行 現・六代目桂文枝さんが、桂三枝時代に画家の黒田征太郎さんと手がけられた、絵本落語シリーズの1作目です。 道頓堀川に住むカメのカメ吉は、川の水質汚染から湿疹や首の腫れがあらわれ、父と別れてきれいな川を目指すこととします。父は「昔は道頓堀川もきれいだった」といいます。川の汚れは人間のせい。ごみの不法投棄だけでなく、なぜか自らも道頓堀川に飛び込む人間。川は人間のものではない。そもそも誰かのものではなく、未来からの預かりもの・・・ 時は流れ、カメ吉の息子と孫は、亡くなった祖父から聞いていた道頓堀川を目指します。話に聞いていたのとは違い、道頓堀川は美しく青い。さて、どうして道頓堀川は生まれ変わったのでしょうか?自然と共存するとはどういうことなのか、落語ならではの愉快なテンポの中にもいろいろと考えてみたい、楽しい絵本です。
-

【古本再入荷】イノチダモン
¥1,200
SOLD OUT
荒井良二/フォイル 2014年7月発行 282✕216m 荒井良二さんの大型絵本です。 すべてのいのちの、生まれてくることの「よろこび」が絵本から飛び出てきます。 あなたとおなじいのちではないけれど、あなたとものと同じように大切ないのち。 水、花、生き物…歌うようにそれぞれのページからあふれてくるいのちの素晴らしさを、お子様にも、大人の方にも。 ぜひたくさんの人の目に触れますように。

-

CUT AND CUT! カッターであそぼう!
¥1,200
五味太郎/アノニマ・スタジオ 2018年7月発行 切れ味バツグンの文房具カッターナイフ。はさみでは表現しきれない細やかさもあり、使えるようになるとなんのことはない便利な道具です。けれどもカッターを初めて手にするときも、「使ってみよう!」と手渡したほうの大人も、すこし緊張を伴う道具でもあります。 絵本作家の五味太郎さんが提案される、カッターナイフ初心者さんでもあるちいさい人に向けた工作のヒントとなる楽しい絵本です。切る、折る、重ねる、くっつける、ぶらさげる・・・「描く」も!カッターをはじめて手にするときに一緒に読みたい、正しいつかいかたの解説つきです。 ひとつの道具を手に取って、使いこなせるようになることのよろこび。自分でお気に入りのハンドクラフトを作って飾るワクワク。子どもだけでなく大人も一緒にどうぞ!
-

永遠のおでかけ
¥550
SOLD OUT
益田ミリ/毎日新聞出版 2018年1月発行 「永遠のおでかけ」、誰かの命の終わりが自分のすぐ近くにやってきた。その人を想い、懐かしみ、あれをしておけばよかった、こんな話をしておけばよかった、と考えるけれど、それはいま私が生きていて、その人は心の中でちゃんと生きているから。 なにかを処分したところで、思い出は失われない。ずっと悲しみにとらわれていなくても、あたたかい思い出をふとしたことで思い出すのは、いま私が生きているから。益田ミリさんが、おじや父との別れから、たしかに一緒に生きてきた日々やこれからをつづったエッセイです。

-

いこうよ ともだち でんしゃ
¥550
SOLD OUT
視覚デザイン研究所 作・くにすえたくし 絵/視覚デザイン研究所 2012年12月初版 2014年第8刷発行 雪の降る街に暮らすしろくまくんから、「あそびにおいでよ」と届いた手紙とプレゼント。急行「ともだち号」に乗って、ゆきのまち駅へ出発です。でも、あまりの大雪に、「ともだち号」は途中で立ち往生!助けに来てくれるのは・・・ いろいろな列車だけでなく、はたらく乗り物やいろんな仕事についても読むことができるしかけ絵本です。たくさんの音や歌声も聞こえてきますよ!

-

本や紅茶や薔薇の花
¥880
SOLD OUT
陸奥A子/河出書房新社 2016年5月発行 1972年に漫画家として少女漫画雑誌「りぼん」の増刊号でデビュー後、今も活躍される陸奥A子さんのイラストモノローグ集です。 1970年代から80年代の少女まんが雑誌りぼんにて、「おとめちっく」なまんがでブームを起こし、のちに女性誌へと舞台を移され、長い間女性のこころを描き続けてきた陸奥さん。 恋へのあこがれやささいな日々への感謝、もう会えない誰かを思う気持ちまで、やさしいことばと描き下ろしイラストの一冊です。 「本、紅茶、薔薇の花」は、眠くなるために必要なものたち、と。タイトルとおり、気持ちをととのえたい時に開くとほっとする、一日の終わりに開きたい本です。

-

アフリカの音
¥880
SOLD OUT
沢田としき/講談社 1996年3月発行 「アフリカの音」、ときいて多くの人が思い浮かべるのは、リズミカルな打楽器の音でしょうか? この絵本に登場するのは、ジャンベ。主に西アフリカ地域で演奏される太鼓です。 西アフリカは太鼓とダンスの豊かな文化を持つ地域、人々の生活に根差しています。 木をくりぬいて、いのちを終えたヤギの皮を張って作ったジャンベ。いのちは楽器に生まれ変わって、うれしいとき、頑張るとき、大地の恵みに感謝するとき、新しいいのちが誕生するお祝いのとき、そして祈りのときに、新しい音となり、ことばとなって、かわいたアフリカの風に乗ってどこまでも届きます。 太鼓の音やリズムに加えて、アフリカのひとびとの日常も、お祭りの日の特別な楽しい時間も感じられる沢田としきさんの絵とことば。「ドン ドン」だけでは表現できない豊かな音を思い浮かべて、心豊かに軽やかにどうぞ。
-

辰巳芳子の旬を味わう-いのちを養う家庭料理-
¥1,100
SOLD OUT
辰巳芳子/NHK出版 1999年3月発行 料理研究家の辰巳芳子さんが、1996年4月から1998年3月まで、朝日新聞に連載されたものをまとめられた本です。 見開き2ページで1つの献立を。右ページには辰巳さんのボリュームあるエッセイを、左ページには写真と手順が。 和食を中心とし、主菜、副菜からおやつまで、12か月の旬の食材を使ったたくさんのお料理を紹介されています。 四半世紀前のものとは思えないエッセイの根底には、引き継がれてきたお料理の基本、身近な旬を取り入れる豊かさ、健やかな心身の育て方、少しの手間をかけるゆとりをもつことなど、現代取り組んでいるSDGsの提言とつながるものばかりのように思えます。